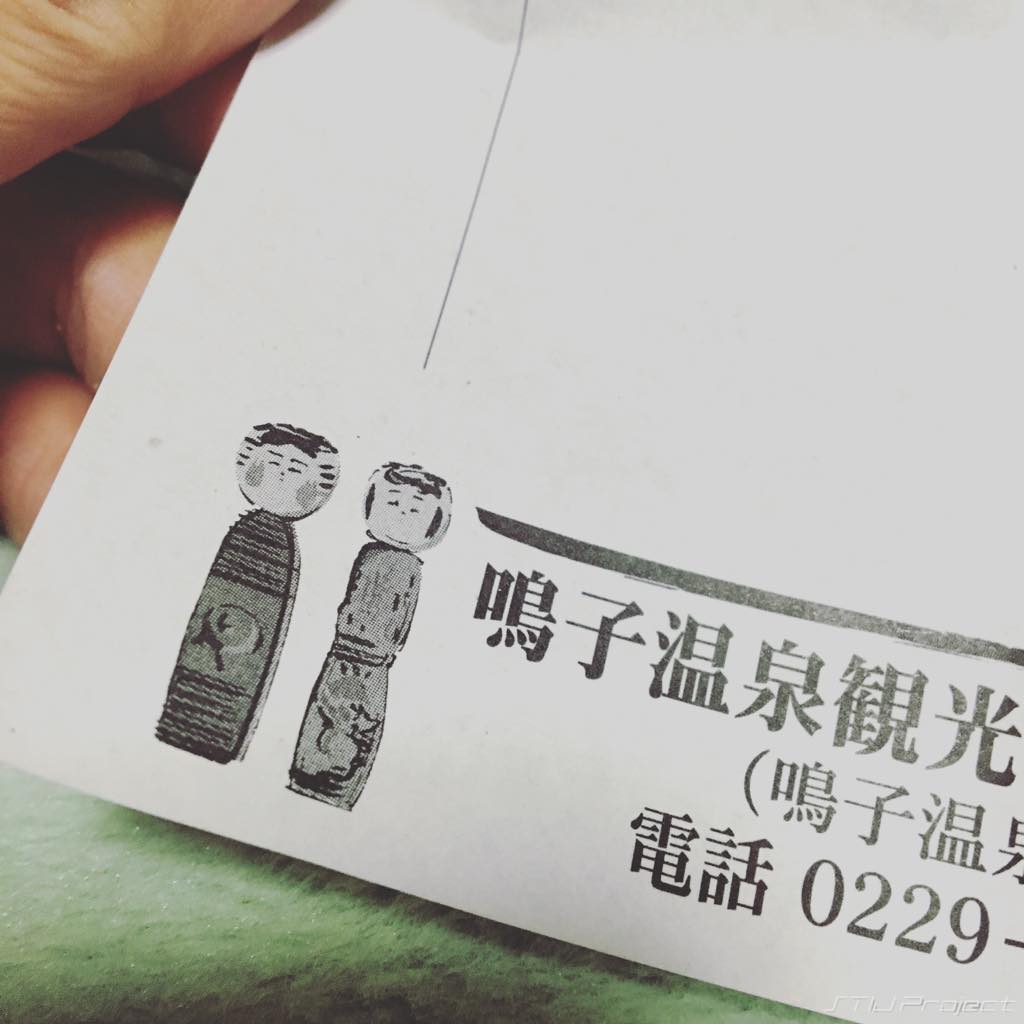タイトルには書いたものの、強いていえば「クレオパトラとツタンカーメンと楠田枝里子を足して3で割った」ような面持ちというのが個人的感想です。白くきめ細かいアオハダの木地、首がクラクラと動く工法は南部系こけしのスタイル。
作品の製作者、松本鶴治工人(1922-没年不明)は1922年3月11日に京都・舞鶴の生まれで、戦後に花巻へ移住し木地を修得しました。戦前は日本画を習っていたとのこと(「全工人の栞」,上p232.)。作品底面の署名は本名ではなく「松鶴 作」と記載されています。
こちらは鶴治工人による色紙。多芸で野生動物の剥製も手がけていたそうです。
さてこの作品、いわゆる伝統こけしの範疇に入れるかそうでないかの判断が人によって分かれるところです。
盛岡・花巻周辺のこけしは系統系列主義で捉えると伝統こけしの 「枠スレスレ」か「枠外」に分けられてしまうものもありますが、個人的にはこの「枠スレスレ」な作品が気になってしまうのです。伝統性とは何かを考えるとき、「何をもって線引きをしているのか」、「誰によって線引きがなされたのか」、その外周や辺縁を見ることも必要なプロセスではないかと感じます。
「辞典」によると、この模様を考案した北本武氏(1913-1984)は福島の二本松生まれ。
盛岡駅前通(当時は平戸という地名だった)でお菓子屋さん「玉屋」を営んでいましたが、こけしに興味を持ち店内で売り始めたところ民芸品の販売を本業にしてしまったという方です。
ついには自分が考案した模様を安保一郎工人や松田精一工人の挽いた木地に描くようになってできた作品がこの「北本武型」で、店舗に隣接してこけし製造工場まで作ったとのこと。
木地製作で南部系工人と接点を持っていることからいわゆる伝統こけしの文献で紹介されるようになりましたが、作品についてはもはや郷土人形の範疇であると一刀両断しています。
ただ、キナキナの製法が確立されていた地域に、他地域のこけし製法が加わり、さらに官民による観光土産の商品企画が加わり…という岩手県央部における木地・民芸産業の歴史的な流れが一本の作品から垣間見える点でとても興味を惹く作品と言えます。
3人の描彩者とその作品
初期の作は北本武本人の描彩であったが、のちに大沼俊春が自挽描彩をするようになり、現在では花巻の松本鶴治が製作している(松鶴型)。したがって北本武型には三人の描彩者がいることになる。(「辞典」,p163)
ということで集合してもらいました。
左から北本武氏による面描作(1)、大沼俊春工人作(2)、松本鶴治工人作(3)。
(1)は考案者本人が描いたものでこれがオリジナル北本武型となります。首がクラクラと動く南部仕様で、頭を持ち上げると1ミリほど接合部分が見えます。こちらは胴模様のないタイプで鬢飾りの本数は8本。
(2)を製作した俊春工人(1929-2007)は鳴子の大沼甚四郎工人(1882-1944)の養子で、戦後は鳴子から花巻〜二枚橋〜盛岡の間を転居し晩年は平泉に居住していました。盛岡時代は北本氏の工場にいたことがあり、ここで北本武型を修得したと考えられます。
写真の作品の底面を見ると、前所有者のものと思われる「4.8」という数字が鉛筆で記入されています。これが製作年代だと仮定すると平成4年(1992)8月で、近年も北本武型を製作していたことになりますが、この数字が単に「前所有者が入手した年月」である可能性もあります。こちらも南部仕様のはめ込み式で鬢飾りは6本。
ちなみに、赤色が滲んで見えるのは使用している染料(赤色103号・エオシン)の浸潤性が高いためです。
そして記事冒頭写真で掲載した(3)の松鶴作。1960〜70年代初期の作品は写真のように目鼻立ちのはっきりとした面描をしていますが、80年代以降の作品では上瞼が細くなったり、鬢が短くなったりと変化があります。鬢飾りは5本で、6寸で製作された作品には4本の飾り線が引いてあります。
ここで注意したいのは、飾り線の本数が何本であるかということは作者や製作時期を判断する際の材料のひとつに過ぎません。作品から自分自身が何を感じ、考えたかが大切であることは忘れてはなりません。
以下の作例を見てみましょう。

底面に「松鶴 北本武型」と記載されている作品。
描彩がなく、キナキナの変化形の位置づけで製作されたのでしょうか。
この作例から推測されるのは「北本型」とは木地の形状であり、描彩をもって「型」を決定づけるものではないということです。それゆえに工人ごとに描彩のバリエーションがあるのだと思います。
「玉屋」その後
こちらの開運橋通店舗のほか、大通りサンビル(岩手県産業会館)1階にも店舗を持っていましたが閉店。開運橋通店舗は「玉屋ビル」とかつての屋号が残っています。大きいマキネッタのオブジェが目印の喫茶店「カプチーノ 詩季」と居酒屋「じょ居」が現在営業しております。